
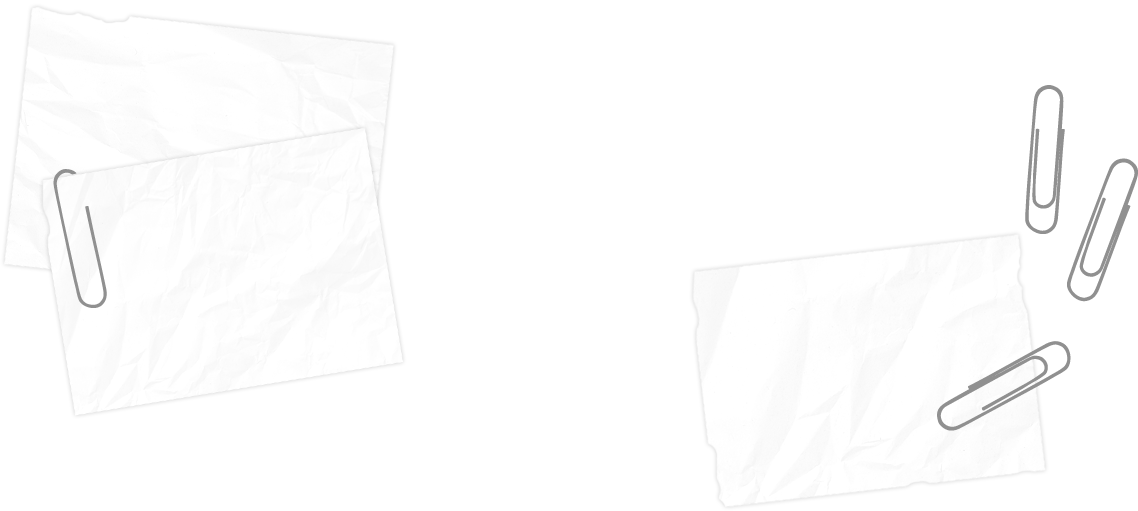
2018年11月の話
泣かずに書けない
松下育男
今週の水曜日の夜に表参道に行ってきました。スパイラルスコレーの詩の教室を覗いてこようかなと思って。
暗くなってから行ったんだけど、その日はたまたまハロウィンで、渋谷に向かって歩く妙な格好の人に交じってスパイラルのビルに向かっていた。僕が担当していた夏の教室の時は、教室が始まる午後7時前ってまだ明るさが残っていたんだけど。さすがに最近はその時刻にはもう夜になっている。夜の詩の教室っていうのもそれはそれで悪くはないんだけど、何ヶ月か前の明るい時を知っているから、歩いていて妙に寂しくなる。
今さら夜が寂しいってトシでもないんだけど、どこかに人の本能みたいなものが僕の中にも残っていて、暗くなるとすごく自分が小さなものに感じられてしまう。暗くなったら早く洞窟に帰らなきゃって、大昔の人の気持ちが湧いてきてしまう。そこまで時間を遡らなくても、情けない気持ちになって、母親の割烹着の後ろに隠れてしまいたい。そういう子供の時の気持ちになることがある。いくらハロウィンのにぎやかな飾り付けの通りを歩いていても、頬に血のりをつけて仮装をした十代の女の人たちの傍を歩いていても、いや、その華やかさの中の夜だからこそ消え入りそうな気持ちになる。
この消え入りそうな気持ちって、確実に詩の入り口に通じているなと考えながら歩いていた。詩に感情は邪魔者、みたいな扱われかたをすることがあるけど、情に流されることによってどんなにひどい目にあったかを先の戦争で思い知らされたことはわかっているし、そういうことを言いたい気持ちがわからないわけではないけど、詩を書くのが人である限り、感情からは逃れられない。問題は情感や感情だけにあるのではなく、冷静な思考の方にだって少なからずあったんじゃないかなって思ったりもする。人って、感情を隠そうとするその手つきにも感情がにじみでてしまうものだということ。
☆
僕の詩は、現代詩の中でも感情や情感を前面に出している方だと思う。ある編集者にかつて「松下さんの詩は嘆き節にならないように気をつけてください」とアドバイスを受けたこともある。自分が感情を前面に出した詩を書いているって、そういうの、自分では若い頃はすごくいやだった。もっと理知的な詩を書きたいと思っていた。心ではなく頭で詩を書きたかった。で、それなりに試みた。本来書けてしまう詩ではない詩を目指さなきゃならないんだと思い込んでいた。でも、そういうの、やっぱり無理がある。人から借りた服を着ているようなものなの。
で
詩を書くときに、
こうしなければならない
とか
こうすればよく見える
とか
こうすれば賢そうに見える
とか
こうすれば人の詩に見劣りがしなくなる
とか
考えるのやめたの。
どうせつまらない詩を書くことになるのなら、決まりごとなんか忘れて詩を書こうと思った。書けてしまうことにひたすら添ってみようと思った。情感が過ぎるとか言われたってかまわない。だって、この詩は僕の詩だから。僕が書きたいように書く。
書き上げた詩が、かりに中年男の情けない愚痴になったとしたってそれでもかまわない。つきつめたところそれが僕の書きたいことならそれでいいと思った。だってそこに自分がいるんだからそういう詩を書いてしまうわけ。当たり前の行為をしていこうと思った。自分だけは言葉のなんたるかを熟知していて、特別なところにいてわかったような詩が書ける。そんなことなんてありえない。
他の人と同じ能力を持って
他の人と同じ感覚を持って
他の人と同じ言語を使っている
それでも自分にしか書けないことがある。
不思議だなと思うけど、それが生きている意味だと思う。
人が読んでどう感じるかを検証しながら書くのは大切なこと。でも、それによって自分の書きたいことや書きたい方法を我慢する必要はない。放っておいても自分の中から自然に出てくるもの。それをほかの何よりも大切にしようと思った。
☆
で、話をもどすと、表参道の詩の教室に行きました。3日前に。秋の教室は川口晴美さんの担当。僕の話みたいに、後半になると声が嗄れるほどいっぱいいっぱいになって話すんではなくて、川口さんはおとなの話しぶり。すごく話すことに慣れていて、落ち着いて聴けたし面白かった。
今週の川口さんの話は「詩を読むことが詩を書くことに繋がっている」っていうことで、わかりやすくそのからくりを説明してくれていた。詩を読むっていうのはそれ自体が創作なんだよと言っていた。まさにそうなんだよなって思いながら僕は聴いていて、詩を読むっていうことは、書かれた詩を受け取るだけではなくて、そこにその価値を与え返す行為でもあるわけ。
そこが詩を読むことに慣れていない人には理解できないところなのかも知れない。つまりね、詩を読むっていうのは詩を感じるっていうことだから。だから詩を読むと言わずに、詩を感じると言ったほうが正確なのかも知れない。
よく、詩はわからないけど読めるっていわれるけど、そういうことだと思う。わからないけど感じているわけ。感受しているわけ。いいな、と思う比喩があって、でもその比喩がどうしていいなと感じたのかを説明することはすごく難しいこと。ただそう感じてしまうわけだから。
で、その話にも関係してくるんだけど「詩は読むのが困難だ」という考え方が昔からある。詩って、人それぞれに勝手にその思いを書いたものだから、読み手は完全には書いたものがわかるはずがないという考え方。
その考え方は正しいと思う。人が書いたものが完全になんてわかるはずがない。というか、書いたものを完全にわかるってどういうことだろうって思う。「完全にわかる」ということがそもそもありうるのだろうか。そんなものどこにもない。まったくない。単なる幻想。
人が考えていることが理解できないように、人が言っていることでさえ完全には理解できていないもの。もともと言葉って完全には通じないものだと思う。で、その完全には通じないものだからつけ入るスキがある。完全には通じないから完全に通じるよりもすごいものを受け渡せる。通じない部分があるからそこを利用して詩は書かれているんだと思う。その利用の仕方が詩の技術の身に付けかたなのかなと思う。
☆
言葉は通じない。だから詩だって完全には通じない。だから傑作と言われる作品がここにあっても読む人によって受け止め方は違う。違うけれども、その作品が与えてくれる衝撃の深さは、なぜか多くの人が似たように受け止めることができる。そういうことなのかなと思う。
すごい作品の受け止め方には、共通の部分というものが確かにある。それって不思議だなと思う。例えば石原吉郎の詩を僕が読んで感銘を受ける。まただれか他の人が読んで感銘を受ける。それってすごく不思議なことだなと思う。かつて生きていた一人のオジサン。石原という苗字のオジサンの書いたものを胸の深いところで受け止めている人が別々にいる。その「別々」ってすごく不思議ですごく素敵なことだと思う。
読み手同士って、離れているんだけど離れていない部分があるっていうことだから。自分の中のある部分と同じものを持っている人がどこかにいるっていうことだから。それって涙が出そうになるほどすごいことだと思う。
☆
胸の深いところで受け止めることって、ただ本を読むという行為の中だけではなくて、もちろんその人が生きているそのことに大きく影響しているわけで。僕は長い間生きていて、でも詩のことばかりを考えて生きてきたわけじゃない。むしろ日々の瑣末な用事や会社の出来事におろおろしながらほとんどの時間を過ごしてきた。
でも、そうしておろおろしている自分の奥底に、例えば石原吉郎の詩の1行がたゆたっているのね。意識していなくても受け止めて、自分なりの価値を与え返した詩が僕の中に転がっている。
詩の1行って
自分を支えてくれるほどには
太くて強いものではないかもしれない
詩の1行って
自分の生き方を指し示してくれるほどには
先はとがっていないかも知れない
でも詩を読むっていうことは、ただ理解をすることではない。ものを表現するっていうことの素晴らしさ。自分がそこに関われることの恐れやあたたかさ。そういうものを感じながら、そういうことを忘れずに、詩を読み、書いていきたいと思う。
泣かずに詩が書けるか
って思う
僕は昔、ぼろぼろ涙を流しながら詩を書いたことがある。長い長い詩を書いたことがある。まさかぜんぶの詩をそうして書いてきたわけではないけど、でも心持ちはいつも同じ。
人から見て、どんなにつまらない詩であっても、自分の中では全霊を込めて立ちむかっていきたい。優れた詩ができるか、つまらない詩ができてしまうかっていうのはそのあとの問題。たいしたことじゃない。
大切なことはたいてい手元にある。自分が今自分の詩になにをしてあげられるかっていうこと。詩にあとでなにかをしてもらえるかっていうことじゃない。
書いているその時に
書いているその場所に
すべてがある
書いているまさにその時に思い浮かぶフレーズに、生きていることのすべてがある。詩を書くってそういうことだと思う。カッコつけてる場合じゃない。
泣かずに詩が書けるか
ぐっとこないで生きていられるか
って
思う
ここにこうして私がいる
そのことの切なさを込めずして
なんの創作だろう
失敗作でも結構。つまらない詩ばかり書けてしまう日々でも結構。大事なのは、その詩のできあがりにあるのではなく、詩を書こうとする自分の手元を見つめることにある。それ以外にはない。
詩とは常におごそかに向かい合っていたい。
自分が選びとった詩は
わんわん泣きながら書いていたい。
書き続けていたいと思う。
詩を書くのは
詩を書くそのことのため以外にはない。
詩を書いている時がすべて。
その時に感じているこの世に対する震え。それ以上のものを僕は知らない。
泣きながら生まれてきたんだから
泣きべそをかきながら生きて
しっかりと泣き疲れて死にたい。
そういうことなんです。